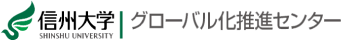これから注目の国!マレーシア!
宮西 夏帆さん
学校教育教員養成課程
留学期間:2015年9月~2016年5月
留学先:マラヤ大学
留学先大学について

信州大学の敷地と比べ、マラヤ大学はかなり広いため、(キャンパス内の寮から講義棟まで徒歩20分以上)バスで移動していた。私が留学としてマレーシアにいた頃は、テロに対する警戒が特に強い時期だったので、日本大使館から送られてくるメールを注意して確認していた。また、日本と比較すると治安は悪いので、外出する際は気を付けていた。大学が首都のクアラルンプールにあるため、近くに大型のショッピングモールがある。そのため、日用雑貨や食料品を買う上では、何の問題もなかった。(和食レストランがあったり、ダイソーなどもある。)大学の運営に関して言えば、寮の管理人が英語をうまく話せなかったり、ISC(国際交流センター)の職員同士で対応の仕方や問い合わせした時の回答に違いがあったり、授業の中では留学生という立場だけで対応が悪かったりなどのことがあった。しかし、これも今思えば、マレーシアという国民性がよく表れたことのように思える。週末にはISC主催のホームステイプログラムが開催されたり、キャンパス内で不定期的にインターナショナルフェスティバルが開催されたりと、マレーシアの文化やその他の国の文化に触れ合ういい機会であった。
学習面について
当初の予定では、イスラム教に関する授業や異文化理解に関する授業を履修するつもりであったが、授業がマレー語で開講されていたり、開講されていない授業もあった。そのため、留学前に立てていた履修計画をすべて変え、前期は語学系の科目を、後期は自分の専門分野を主に履修した。マラヤ大学の(留学生の)履修のシステム上、ネット上で事前に登録した授業がとれないというケースが多々あるので、注意が必要である。また、信州大学とは違い、マラヤ大学のほとんどの授業は1コマ3単位3時間である。そのうち、2時間は講義型、1時間はチュートリアル(学生同士の意見交換やプレゼンの発表)である。特に、チュートリアルに向けた予習や準備が大変な授業があるので、要注意。1セメスターに4、5科目の履修がちょうどよかった。最後に、授業によって、授業の質が全く異なるので、オリエンテーションにいったり、教授と相談して受講するか決めることが大切だと思う。
生活について

留学して数カ月は、気候・食生活・言語の面で日本とは全く違うので、カルチャーショックを受けていた。しかし、徐々にその生活に慣れていったり、マレーシアの良さに気付いてから、暮らしやすくなっていった。まずは、友達を作って、自分の居場所を見つけることが大切なのだと思った。また、私は長期休みを使って東南アジアの他の国に旅行しにいったのだが、同じ東南アジアにある国でも、国が違うだけで国民性や雰囲気が違って面白かった。
留学で得たこと

私は、この留学を通して以下に挙げる二つのことを主に学んだ。
一つ目は、個々人を見ることの大切さである。私が留学先として選んだマレーシアは、多民族国家の国である。そのため、違う民族がいる中で、どのように一つの国に共存しているのだろうと不思議に思っていた。しかし、実際にふたを開けてみると、民族間の対立があり、違う民族に対して陰で差別的な発言をする姿が見られた。しかし、そのような対立はあったものの、実際にそれぞれの民族の方と対話をすると、優しくて人思である方ばかりであった。また、私は留学する前は、近年の外交的問題により、韓国や中国に対して悪いイメージを抱いていた。しかし、ルームメートであった韓国人やクラスメートの中国人と日々の生活を共にする中で、「この人たちも、(外交的対立により互いに悪い印象を抱くときはあるけれど、)嬉しいときは一緒に喜んだり、同じような悩みを抱えたりと、同じ人間なんだ、友達なんだ!」と思うようになっていった。また、私が帰国する前に、韓国人のルームメートから、「私は、あなたと出会ったから、日本に対してのイメージが変わった。過去の歴史から、日本に対して良くないイメージを持っている韓国人もいるけれど、でも、私は個人を見ることが大切なんだって気付いた。どの国にも、悪い人・いい人はいる。また、あなたがルームメートだったから、日本行ってみたいと思うようになった」と言われた。私たちは、外交的対立の中で起こるトリックや、学校教育の中で身に付けさせられてきたステレオタイプによって、外国の方を悪く見たり本当の姿を見失っている可能性がある。個々人とのコミュニケーションによって他人によって与えられたフィルターを取り払うことが、本当の異文化理解なのではないかと痛感した。また、「他人によって与えられたフィルターを払う」ことに関して述べれば、外国を見るときも同じことが言える。未だに日本人は、欧米への憧れが強く、アジア圏の国を低く見る傾向があるように思われる。実際に私も、友達から「マレーシアで生活して、大変じゃなかった?なんで欧米に行かなかったの?」とよく聞かれる。確かに、日本や欧米に比べれば、不便だと思うような時もあった。しかし、友達の家にお邪魔した時は、家族のように私を受け入れてくれたし、日本では見られないような温かさも数多くあった。外国に行って異文化に触れたことのない人から見れば、「日本が恵まれている」「東南アジアは貧しくて生活しづらい」と思われているのかもしれない。しかし、先にも述べたように、他人からのフィルターからその国を見るのではなく、自分の肌で実際に体験することで、その国の本当のよさが見えてくるのだと思う。
二つ目は、英語の使用に関して、思うことが多々あった。私は留学に行く前は、「グローバル人材=英語ができる人(特にネイティブのように英語が使いこなせる人)」だと思っていた。しかし、ネイティブの英語とは違う英語をマレーシアで聞いたりする中で、グローバル人材とは英語ができるだけの人を指すのではないのだという結論に至るようになった。さまざまな英語が話されている中で、(時には自分にとって分かりにくい英語であっても)それらの英語を理解しようとすることが大切なのだと思ったし、さまざまな価値観や考えが存在する中で、自分の考えが主張できることが大切なのだと思った。また、マレーシアでは英語を話せない方もたくさんいる。しかし、そのような方と出会ったときに、英語だけを押し通したり、そのような方たちを見下したりするのではなく、「現地の言葉」を勉強してコミュニケーションをとろうとすることが重要なのだとも実感した。
後輩へのアドバイス

留学する目的を「語学力向上のため」とするのは、もったいないと思う。留学先をする際に、いくつかある提携大学の中から大学を決めると思うが、それぞれの国や地域によって得られるもの・学べるものが違うと思う。留学の目的をまずははっきりとさせて、それに合った大学を選んで欲しいと思う。 また、留学というと、何となくアメリカというイメージがあると思うが、他の選択肢にもぜひ目を向けてほしい。「なんとなくアメリカがいい」と思っている人は、アメリカで何が得られるのか、もう一度考えて欲しいと思う。留学は、さまざまな人の価値観に触れるいい機会、ぜひ、「生の声・生の雰囲気」というものを大切にして欲しい。